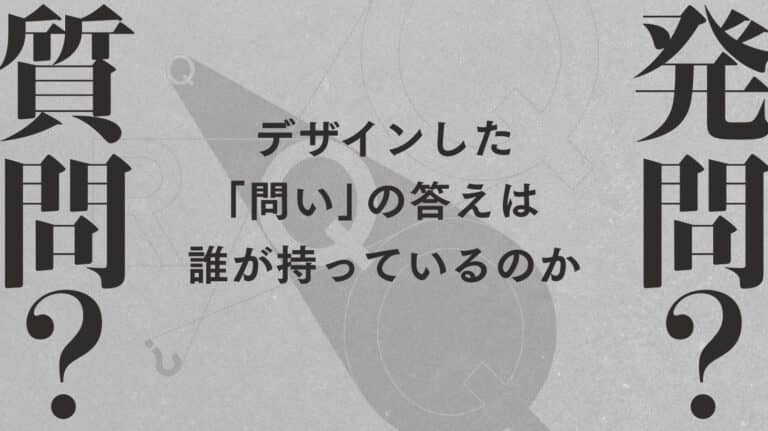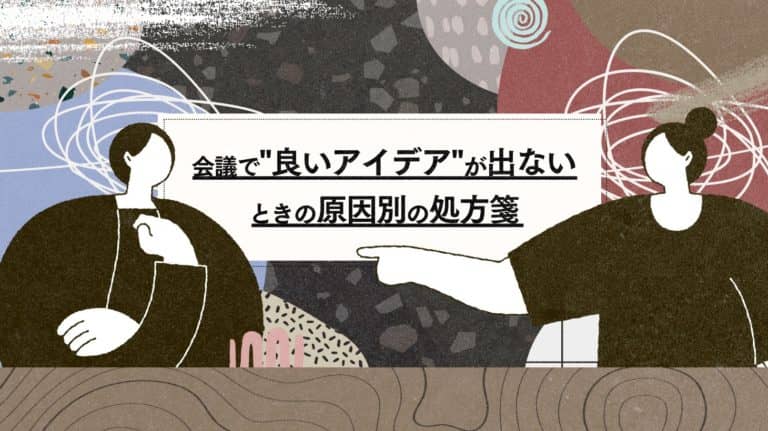CULTIBASE Radioは、人やチームの創造性を高める知見を音声でお届けします。 CULTIBASE Radio マネジメントの28回目では、CULTIBASE編集長の安斎勇樹と株式会社MIMIGURI Co-CEOのミナベトモミが、「なぜか誰も教えてくれない「対話の教科書」に書くべき基本」をテーマにディスカッションしました。
※今回は、先日YouTube LIVEにて公開収録したものを、トピックごとに編集してお届けします。
- CULTIBASE Radioおなじみ、「マネジメントの教科書に書いておいてほしいこと」シリーズ。今回は「対話の教科書の1ページ目」を考えたい。
- 対話は、その重要性は合意されていても、実際にやるとなるとうまくいくイメージはつかない、ということが多い。そもそも、組織によってはコミュニケーションを取る機会が全くないこともある。
- 「対話的な機会を作ろうとしているけど、なんかうまくいかない」という場合の問題点として、「相手への根本的な関心がない」というものがあったりする。あいづちや質問など表層的なリアクションはしても、あまり相手の話をそもそも聞きたいと思っていない。
- 企業によって、「自分自身のことをどの程度“発露”させていればいいのか」という程度は違うが、対話をするにあたっては「相手の、今は見えていない部分への関心と想像をもつこと」が重要となる。これが、対話の教科書の1ページ目となるのではないか。
- ミナベがコンサルとして入っている組織でも、それができていないと感じたらすぐに目の前でアジェンダを棄却し、「今あなたが話したいのはなんですか?」という問いを投げかけるという。対話は、まず相手に興味をもつことが肝要だ。