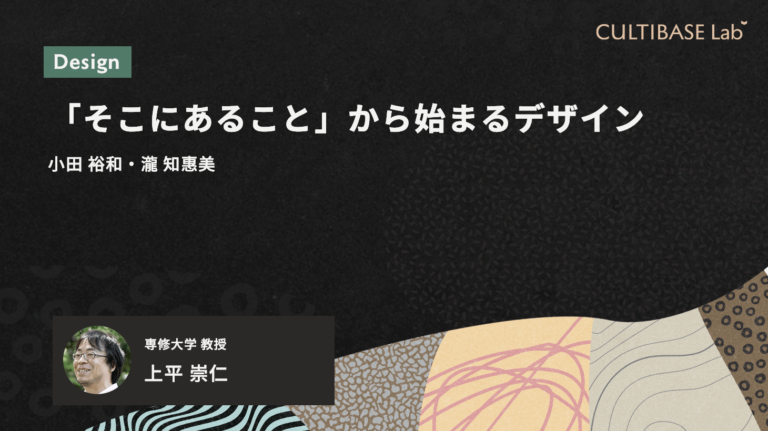「事前に計画すること」は、わたしたちのいま・この瞬間に焦点をあわせる感覚を弱体化しているのではないか? そんな問いを起点として「計画」に対抗して生きるための知を探索していく、上平崇仁さんによる本連載。その第5回では、世界に応答していくためのインターフェイスである「身体」と「創造性」の関係性について、美術系教育機関における「体操」の事例を紹介しながらひも解いていきます。
何事も事前に計画することが強く求められる時代です。しかし、先回りして決めることで、周囲の余白は消え、「いま・ここ」に生起するありえたかもしれない可能性を見失う危険も伴います。前のめりになってスピードをあげることが是とされる中で、わたしたち生活者は、いかにして一期一会の世界との出会いに応答していくことができるのでしょうか。
この連載では、あえて常識とは逆のフレームから今の時代を探索し、そこから生活者目線のデザインのあり方を探ることを試みています。これまでの連載では、以下のようなテーマを綴ってきました。
第1回:「計画」に対抗して生きる。イマ・ココを味わう身体感覚を呼び戻す
第2回:リフレクションは〈誰〉がするのか? わたしたちの中に存在する「2つの自己」にまつわる問い
第3回:「地図」が旅行者の動きをコントロールする時代に、「状況論」から学べること
第4回:一期一会の世界との出会いに応答していくために、前景化されない「身体」の声に耳を澄ます
第5回となる今回では、前回の主題であった「身体」への着眼点を引き継ぎ、具体的な身体と創造の実践を探っていきます。
身体運動を取り入れた創造活動
身体は、環境と相互作用してその変化を描きだし、わたしたちの言葉や概念を形成します[1]。その点で、身体は単なる容れ物ではなく、わたしたちが創造するものごととのインタフェースでもあります。身体的な活動と創造する営みはそれぞれ別々に捉えられがちですが、意識の水面下で密接に相互作用しあっているのです[2]。
過去の偉大な教育者たちもその重要性に気づいており、創造の基礎的なトレーニングとして身体運動を取り入れようとする試みが古くから行われてきました。具体的な事例をいくつか紹介します。
1)イッテン体操:ヨハネス・イッテン
モダンデザインの源流となり、世界中に大きな影響を与えたバウハウス。無駄を省いた合理的なデザインのイメージをもたれがちですが、根幹にあったのは、分化しがちな諸領域を「統合」しようとする精神であり、身体を使ったパフォーマンスや舞台芸術なども盛んでした。
その中でも、初期の基礎課程のマイスターだったヨハネス・イッテン(1888-1967)の造形教育は独特です。イッテンは、描く前に全身の緊張をほぐすために、いち早く体操を取り入れたことが知られています[3]。いわゆる「イッテン体操」です。
イッテンは、毎朝一日の始まりに、彼は生徒たちにまず体操を行わせた。そこには瞑想の要素も含まれていた。この体操によって、彼らを縛るわだかまりやこわばり、そして「アカデミックなもの」全てが取り除かれ、きたるべき体験を受け入れる態勢が行う。体操には3種あった。第一に手足を動かし、全身を屈伸させること。この時、背骨の運動がとても大事になってくる。 第2には、立ったり座ったり横たわったりした姿勢で、極力体を動かさずに保つこと。そうやって思考を集中させると、徐々に緊張が解けていく。内臓をリラックスさせるには、このやり方しかない。緊張をほぐし、体をバランスよく調和させる方法の第3は、声の振動を利用するものだ。生徒は発声法の練習をしなければならない。体のどの部分で声が振動しているか、わかるようにならなければいけないのだ。
――ドロレス・デナーロ『ヨハネス・イッテンによる芸術教育の方法』石川潤 訳
図版出典:
Students in one of Johannes Itten’s “unlearning” exercises at the Bauhaus
https://arthistoryteachingresources.org/2018/03/learning-and-unlearning-using-hands-on-bauhaus-exercises-in-art-history-classes/
イッテンは、こう考えていました。制作者の身体は、まさしく描くための道具であり、世界に対して全身の感覚をひらいていくことこそが創造の基盤である、と。
単に対象を模写するのではなく、より表現の本質に近づきつつ描くための訓練として、例えば、植物のアザミを触ってとげとげしさや痛みを感知した上で再度スケッチする、教室中で全員が虎のように吠えて唸りながら虎の絵を描く、全身を使ってスウィングとリズムを紙の上に素描する、などの風変わりな実践の記録が残っています。
イッテンが行った造形教育は、日本にも早くから輸入されていましたが、最近では言及されることもすっかり減りました。デザイン教育の裾野はここ20年ほどで広範囲に広がったとは言え、広がったのは汎用的に使える「思考」的な側面に着目するもので、言ってみれば「脳」的なものです。身体感覚をひらいていく地道な訓練は、コピーしにくく膨大な手間暇がかかることもあって、“クラシカル”なものと見なされつつあるのかもしれません。
2019年にはバウハウス誕生から100周年を祝うイベントが世界中で行われ、日本でも桑沢デザイン研究所主催のイベントにおいてイッテンの授業が再演されました[4](もちろん私も参加し、体操してアザミを描きました)。 イッテンのような「いま・ここ」の身体性を重視したトレーニングは、いまの時代にこそ非常に意義深いはずですので、再評価したいところです。
2)体操のデザイン:杉浦康平
1966年に桑沢洋子を中心に設立された東京造形大学。大学名に冠された「造形」とは、ドイツ語の“Gestaltung”に由来し、バウハウスを受け継ぐ教育理念を持つ美大として知られます。この大学の開学期には錚々たる面々が集い、斬新な美術/デザイン教育が行われました。グラフィックデザイナーの杉浦康平(1932-)は、この時、(実現はできなかったものの)「体操のデザイン」を構想したと証言しています[5]。
“これは体育の教師の反対で実現はしなかったけれど、「体操をデザインする」と言う授業も試みようとしていました。例えば卓球台の真ん中に鏡を置いて、45度から打ち込むと45度方向に跳ね返るから、 台の同じ側の両端にいる生徒同士が、鏡で跳ね返る球でピンポンする…などといったように、既成のルールをちょっとずらした新しい競技を考えると言うことを含めて、体育の単位にしてもらおうとした。 一事が万事、そんなふうにして学生たち、教えるスタッフも一丸となって、新しい方法を模索していた”
――杉浦康平インタビュー『アイデア No.324』収録 2007.9 P.011
半世紀後のいま聞いても、非常に攻めた取り組みで驚かされますが、特に興味深いのは、こうした一連の取り組みが着想された経緯です。杉浦によると、当時造形大は都市文化と距離がある八王子の山あいに立地していたため、学生たちは自分たちでできることを見つけ出す力を身に付けなければならなかったし、教える側も新しい教育方法を模索しなければならなかった。そこで環境や生活の中からテーマを見つけてデザインしよう、とする訓練を繰り返した。すなわち、「自分自身に〈主語〉を置く」という発想で相互に学びあおうとしたのです[6]。
この時期に生み出された杉浦の方法論は、主語を転換させることから世界を組み替え、新しいリアリティを視覚化しようとするもので、そのアイデアは、のちの一連のダイアグラムの傑作『時間軸で見る日本列島(1971)』にもつながっています。
杉浦らが取り組んだように、与えられないところで「自分たちでできることを見つけ出す」ことは、デザインを学ぶ上で極めて重要な態度です。むしろ、いまのような渾沌とした時代の中でこそ、大学生たちに「体操のデザイン」のような一人称の視点を再考してもらいたいところです。そのためには、三人称ではないやりかたでものごとを捉え直すことが欠かせませんし、「体感」することを抜きには成り立たないでしょう。やはり、身体性が起点になると言えます。
3)野口体操:野口三千三
東京藝術大学で長年にわたって体操を指導した野口三千三(1914-1998)は、人々が身体を使った活動を支援するために、「野口体操」の理論と実践を発展させました。野口は「あらゆる器官・組織・細胞の全てで、解放されている部分が多ければ多いほど、新しい可能性を持つ。すなわち、次の瞬間に仕事できる筋肉は、いま休んでいる筋肉だけである」と主張し、積極的に全身の力を抜く訓練を指導しました。芸大生からは「こんにゃく体操」と呼ばれて親しまれたそうです。
野口は、身体活動の中でも特に無意識で行われがちな「呼吸」の仕方についても、ギリギリで永遠に完結しない問いとして重視しています[7]。
「息の仕方が生き方である」ということは、その人が生活の中において、どのような呼吸の在り方をしていることが多いかの傾向によって、その人の性格や、からだの中身のあり方が決定されていくからである。〈中略〉
いずれにしても、性格や行動が、呼吸と密接不可分の関係にあり、呼吸法の意識的練習によって、性格や体質を変えていくことが可能だと言うことなのである。
―― 野口三千三『原初生命体としての人間』岩波現代文庫 P137
図版出典:https://www.noguchi-taisou.jp/noguchitaisou/photo.html
息することは、生まれたばかりの赤ちゃんを始め、誰もが当たり前にできること。そう思いがちですが、野口は、そんな原初的な活動にこそ生き方が反映されるとして、呼吸の仕方を自分自身の生き方の問題として捉えるよう、強調しています。
野口が言うように、たしかに、すべての身体の動きは呼吸により始まり、逆に呼吸や発声は、身体のあり方によって決定づけられています。そう言われれば、ほとんどの人は自分で経験したことのあるさまざまな運動、武道、創造などの場面において、呼吸の仕方と身体の動きが密接に関係していたことを思い出すでしょう。
足の裏の感覚を観察してみよう
その他、ここでは紹介しきれませんでしたが、演劇[8]、インプロ(即興演劇)[9]、パントマイム[10]などの全身をつかった身体表現トレーニングも挙げられます。
ファシリテーター: 藤倉健雄(カンジヤマ・マイム) 主催:上平研究室
2018年6月12日
こうした身体を使うトレーニングは、専門家向けの訓練としてだけではなく、誰が取り組んでも、身体と創造の深い関係についてさまざまなことを気づかせてくれるでしょう。ただ、簡単にできるようでなかなか難しく、指導者無しではハードルが高いことも多いことも事実です。
そこで、私が考えたごく簡単な実験を紹介します。野口三千三は「自分の身体の僻地開発することを考えるべきだ」と言っていますが、その代表的な僻地として、意識されることの少ない「足の指」の仕事を観察するものです。
まず、靴を履いた状態でどこかの階段の前まで移動して、その階段を下りるときの様子を自分で丁寧に観察(Observation)してみましょう。観察することはデザインの基礎訓練のひとつです。
ゆっくりと階段を降りると、爪先が階段のヘリから少しだけはみ出すことに気づくと思います。それを理解した上で、足の裏に全意識を集中しながら階段を降りてみてください。
一見すると、ごく当たり前の日常風景にしか見えないかもしれません。これを詳細に書き下すと、例えば以下のようになります。
1)まず、階段を降りる人は周囲を光に満たされた環境の中にいます。2)階段の上から、一段下の段差への距離の見当をつけます。3)ゆっくりと軸足の筋肉を体性感覚で調節しながら急勾配の空間の中に身体を投げ出し、4)動くことによって階段の遠近(※肌理(きめ)の勾配[11])を能動的に探りあてながら、5)一段下の階段の面をめがけて、足の先を着地しています。6)そのとき、すこしつま先はすこしはみ出していることが多いでしょう。7)そのはみ出したつま先は、次の瞬間、そのヘリを足の指でしっかりと掴みながら、8)おなじように身体を調節しつつ次の階段へ移動しているのです。
靴底越しに、普通は意識していない足の指の関節が重要な仕事をしていることを感じることができると思います(上の映像に写っている学生たちは、全員がそう答えました)。不思議なことに、裸足で階段を降りる時には、掴むような感覚はあまり感じません。足の指たちは、地面の感覚が靴下や靴底で厚く遮られているからこそ、なんとか段差を掴もうと必死で頑張っているのかもしれません。おそらく何百万年も前からずっと、足の指たちは大地をしっかりと掴むことを欲しているのです。
あちこちの階段をよく眺めてみると、弱い視力でも確実に視認できるようにヘリの境界が強調されていることに気づきます。それらは段差に検討をつけるための目印であるだけでなく、掴むための足がかりでもあることがわかります。
そして、何かの拍子にその一連のシステムが崩れ、再構成しなければならないとき、――例えば光のない真っ暗闇のとき / 骨折して松葉杖で降りるとき / 筋力が弱まったとき / とまったエスカレータを歩くとき――などに、無意識が支えていることの重要さが前景化されるでしょう。普段あたりまえに行っている行為こそが、改めて身体と環境との緻密な相互作用で成り立っていることに驚かされるでしょう。
身体にもっと栄養を
今回は、事前に計画したことに縛られないための一つの方法として、身体と創造の関係を探る事例に焦点を当ててみました。いずれも「頭で予測する→準備する→感じる」の通常の線的な思考過程ではなく、その場その場にある予期できない変化を感じ、応答することが起点になっています。
仏教では、身体の一部分を個別に意識し、身体全体の調和を取り直す瞑想の修行が知られていますが、瞑想までいかなくても、上記のような観察を通して体の部位を意識化するだけでも随分違います。
身体の各部分に集中すると、不思議なほどいまここに在る意識も変化します。前回の記事で紹介した、村上春樹の「走ることによって、空白を作り出す」という話にも通じますが、単純な運動の実践からでも、解釈次第で創造の深い部分と繋げられることがあるのです。
日頃座りっぱなしを自覚している人は、時には全身の凝りや緊張をほぐし、身体に栄養を与えてみるのはいかがでしょうか。自分の身体が感じていることに耳を傾けようとする態度を持つことで、自分の内側から響く声が確かに聞こえてくるはずです。
“ Don’t think, Feel !〈考えるな、感じるんだ〉 ” (Bruce Lee, Enter the Dragon)
関連記事はこちら
参考文献
[1] レベッカ・フィンチャーキーファー 『知識は身体からできているー身体化された認知の心理学』望月正哉・井関龍太・川﨑惠理子 訳、新曜社、2021
[2]バーバラ・トヴェルスキー『Mind in Motion 身体動作と空間が思考をつくる』渡会圭子訳 森北出版 2020
[3]図録「ヨハネス・イッテン 造形芸術への道」京都国立近代美術館 2003年 P.37
[4]造形教育の源流を探る Bauhaus/バウハウス 再現「ヨハネス・イッテンの授業」https://www.kds.ac.jp/designforefront/20190608/
[5]杉浦康平インタビュー『アイデア No.324』収録 2007.9 P.011
[6]同 P.011
[7]野口三千三『原初生命体としての人間―野口体操の理論』岩波現代文庫2003 P.137
[8] 鴻上 尚史『発声と身体のレッスン 増補新版 ─ 魅力的な「こえ」と「からだ」を作るために』白水社 2012
[9] 上平崇仁「インプロビゼーションとアイデア発想ワークショップ :いま、この瞬間の世界と向かい合うことの意味」 専修大学情報科学研究所 所報 No.82, 2014 https://kmhr.hatenablog.com/entry/2016/10/20/212753
[10]クロード キプニス『パントマイムのすべて』カンジヤママイム訳 晩成書房、2000年
[11]ジェームズ・ギブソン『生態学的視覚論―ヒトの知覚世界を探る』古崎敬訳サイエンス社、1986年
著者プロフィール:
上平 崇仁
専修⼤学ネットワーク情報学部教授。大阪大学エスノグラフィーラボ招聘研究員。グラフィックデザイナーを経て、2000年から情報デザインの教育・研究に従事。近年は社会性への視点を強め、デザイナーだけでは⼿に負えない複雑な問題や厄介な問題に対して、⼈々の相互作⽤を活かして⽴ち向かっていくためのCoDesign(協働のデザイン)の仕組みや理論について探求している。15-16年にはコペンハーゲンIT⼤学客員研究員として、北欧の参加型デザインの調査研究に従事。単著に『コ・デザイン― デザインすることをみんなの手に』がある。