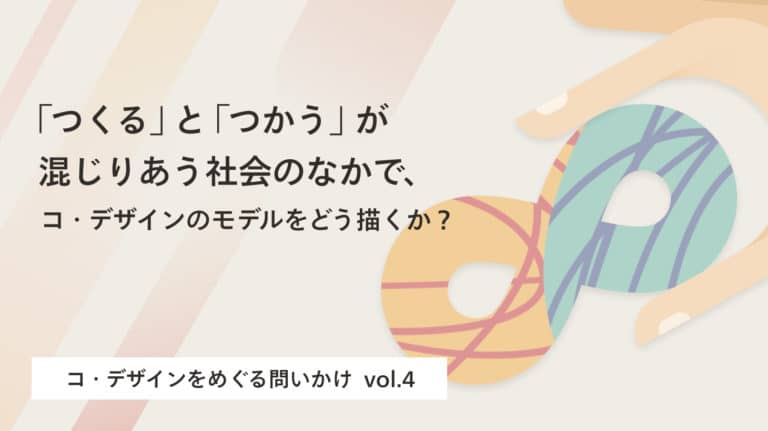世界各地のデザインスクールを卒業したばかりのデザイナーが、その学びを振り返る連載「世界のデザインスクール紀行」。第3回に登場するのは、2019年に100周年を迎えたバウハウスの関連団体であるバウハウス・デッサウ財団が設立した「COOP Design Research」を卒業された佐藤ちひろさん。科学的かつアカデミックな視点からのデザイン研究を通じて、佐藤さんは誰もがデザイン活動に参加する時代における「デザイナー」という専門職の役割を再考していきました。
私は2018年10月から2019年9月まで、ドイツのCOOP Design Researchというマスターコースに留学しました。今回は制作畑出身のデザイナーである私が、デザインスクールに戻ることにした経緯とそこで学んだこと、現在ベルリンで関わっている事業について紹介したいと思います。
社会活動に参加するデザイナーを目指して
大学で国際関係学を学んだこともあり、グラフィックデザイナーになってからも、「デザインは世界をより良くする責任がある」と信じていたし、社会のためのデザインに取り組みたいと考えていました。
その頃の私は、例えば貧困問題への社会的喚起を促すポスターをデザインしたり、寄付を楽しくさせるような仕掛けの広告をつくったりといったカンヌライオンズの受賞作品となるような広告としてのコミュニケーション・アプローチをイメージしていたと思います。
しかし、私のいた環境では、グラフィックデザイナーとして出すべき成果物は、誤解を恐れずに言えば「売ること」でした。デザイナーやフォトグラファーの方とチームをつくり、自分たちで考えたコンセプトを具現化することは大変楽しくやりがいもあったのですが、「何を売るか」をデザインすることは分業化されたシステムの中では、デザイナーの範疇ではなく、少しフラストレーションを感じていたことも事実です。
デザイナーとして働く傍ら、自分の拠点を移してまちづくりに取り組む方や、地域で自分たちのコミュニティをより良くしようと活動する方々とのご縁が増えていき、会社の外で専門外の仕事を手伝う機会が少しずつ増えていきました。
そのなかでも転機となった経験は、いわき市の勿来地区で、原発事故による帰宅困難地域からの避難移住者と元々の住民とのコミュニケーションの改善を目指して計画されたまち歩きワークショップ『くぼたんけん』にファシリテータとして参加させてもらったときの経験です。この日のワークショップではグループごとにまち歩きをして、その時の発見を地図という形式で発表するものでした。さまざまな方が協働してワークショップをつくっていたこと。そして、グループ内での地図の出来栄えは問題ではなく、一緒に街を歩き体験や気づきをシェアすることこそが対話を図るためのデザインツールとして有効だと気づきました。そこで実感したのは、地元コミュニティをより良くしたいと精力的に活動する人たちの創造性だったんです。


ローカルには積極的に活動するクリエイティブな人たちがたくさんいて、そこに課題解決とデザインの本質があるような気がしました。夢見ていた広告的アプローチは、私が目指すものとは違うのではないかとも感じるようになりました。表現するならば、広告になる前の段階に強く惹かれたのです。当時読んだ『HELLO WORLD 「デザイン」が私たちに必要な理由』や『世界を変えるデザイン』などの書籍にも大変影響を受けました。
「完璧な物をつくり上げることより、その過程に意味がある活動もデザインとも呼ばれるらしい」「本当に必要な物をデザインするためには、デザイナーもその過程に参加する必要があるけれど、過去にはどのような事例があるのだろう」と考えるようになり、「デザイナーと社会」を対象にした大学やコースに興味を持ち始めました。
私が留学したCOOP Design Researchを知ったのは偶然です。職場の同僚でもあり友人でもあったデザイナーが何年か前にドイツのデッサウにあるバウハウスに旅行し、学校の存在を教えてくれたんです。
幸運にも合格し、2018年の10月に入学しました。翌2019年は、バウハウス100周年の年だったので、デッサウのバウハウスでも記念イベントが多く開催されました。各国でも記念イベントがあったようで、日本人学生として声をかけてもらったり、世界中から集まったソーシャルデザインプロジェクトのオーガナイザーたちの公演を聞いたり、ドイツ人のアーティストとバウハウスの校舎を再解釈して体験してもらうアートプロジェクトを一緒につくったりと、100周年の年にしか経験できないことが多く、良いタイミングでバウハウスの学生になったと思います。
デザインをサイエンスの側面から研究する

デザインの歴史に詳しい方はご存知かと思いますが、バウハウスは誕生から解散まで何回か移転しています。最初はワイマール校、全面ガラス張りの建物に「BAUHAUS」のロゴでおなじみのデッサウ校、そして1932年にベルリンに移転するもの翌年に閉校してしまいます。COOP Design Researchがあるのは、このうちのザクセンアンハルト州のデッサウ校です。ちなみにワイマールには、バウハウス大学があります。
COOP Design Researchは、バウハウス・デッサウ財団とアンハルト大学が共同して、そしてベルリンのフンボルト大学の協力の元に設立されたマスターコースです(学位はMaster of Scienceになります)。1クラスしかなく、10月から翌9月までの一年間ですが卒業までにはみっちり12ヶ月かかります。生徒数は約20名で、私の入学時は19人でした。
デッサウは東ドイツ時代の名残を感じるジードルング(集合住宅)が多い、こぢんまりとした小さな街で、ベルリンなどの都市部と違って英語はあまり通じません。ただし、アンハルト大学の大学院は、建築のコースが有名で、こちらのコースには世界中から生徒が集まり学んでいます。ですので、キャンパス内はとてもインターナショナルでした(ただ、日本人は毎年あまりいないらしいです。インターナショナルオフィスに聞いてみたものの、私の代はデッサウのキャンパスで日本人は自分ひとりでした)。

日本でも、デジタルをはじめとしたプロダクトをつくるための手法としてのデザインリサーチに注目が集まっている昨今ですが、COOPにあるのはプロダクトをつくるための手法を学ぶデザインリサーチコースではありません。学位のMaster of Scienceが示すように、分野を問わずデザインを科学的に研究するPhDへのブリッジになるように設計されており、読み書きがとても多いアカデミックなコースです。クラスメートたちのデザインバックグラウンドも幅広く、建築デザインが約半数、他は私のようなグラフィックデザイナーや、インダストリアルデザイナー、アーバンアーティスト、アートヒストリアンなど、さまざまでした。
基本的な授業のスタイルは、哲学、社会学、人類学、建築理論など、各担当教授が選んだ課題図書を読んでそれを発表したり、自分たちで再解釈してプレゼンしたりするもので、とにかく文献を読みます。読んだ著者の一例を挙げれば、人類学者のティム・インゴルド、文化人類学者のアルジュン・アパデュライ、歴史家/哲学者のミシェル・ド・セルトー、社会学者のリチャード・セネット、哲学者のブルーノ ラトゥール、アルヴェナ・ヤネヴァ、それからモホリ=ナジ・ラースローややヴァルター・グロピウスといったバウハウスのデザイナーたちの著書など、教授によってバラバラでした。
いま振り返ると、先行研究に多くふれることで、社会や事象を科学的に論じることを理解するための訓練だったと思うのですが、建築畑の出身でもなく、また他の分野でもこれまで論文や哲学に触れてこなかった自分には、課された本が何を言っているかさっぱりわからないことがほとんどで、すごく大変でした。それでも、最終的に読めるようになってくるので人間はいくつになっても成長するんだな、と修士論文を書く頃に実感しました。
正直に言えば、社会的なデザインプロジェクトに実践者として関わる内容を期待していたので、それは叶いませんでした。COOPにはゼミや研究室のようなものはありません。そもそも一年コースではプロジェクトを担当するには短いですし、アンハルト大学はPh.Dコースを持っていないので、学内でPh.D研究室のプロジェクトに参加して研究するという形式も取れませんでした。ここはリサーチ不足だったと感じる部分でもあります。
「ディフューズデザイン」における専門家の役割
大学院のハイライトはテーマを決め、自分で研究する、修士論文です。COOPの場合は、前期の終わりから修士論文のテーマについてのディスカッションが始まります。私は、論文のリサーチクエスチョンを決めるのに大変苦労しました。「社会とデザイナー」という大きなテーマは持っていたものの、そこからうまく絞り込めずにいました。また、せっかく職能に限定されないデザインについて学んでいるのだから、『グラフィックデザイン』というジャンルにはこだわりたくないと、逆にこだわってしまっていました。最終的に、「これまでの経験やモチベーションを軸にしたらいい」と、ひとりの教授からアドバイスをいただき、それをきっかけに「さまざまなバックグラウンドを持った人が、クリエイティブを持ち寄って協働で行う社会デザイン活動のプロセスのなかでは、みんながデザイナーと言える。そのような環境で、グラフィックデザイナーはどのような役割を果たせるのか」といった趣旨で修士論文に取り掛かることにしました。
DESISの創設者であり持続可能性とソーシャルイノベーションについての研究者エツィオ・マンズィーニは、著書のなかでデザインを「エキスパートデザイン」と「ディフューズデザイン」に分けて定義をしています。その分類によればトレーニングを積んだデザイナーが職業として行うデザインはエキスパートデザインになり、そうではない人々が行うデザイン──本来すべての人間が持っているデザイン能力を生かしたデザイン活動──をディフューズデザインとしています。自分の修士論文では、このマンズィーニの定義を借り、ディフューズデザインの活動でエキスパートのグラフィックデザイナーはその能力をどのように活用できるのかを調べようと決めました。
それを確かめる方法として、ベルギーのデザインスクールで、ホームレスの社会復帰プログラムの一つである「ホームレスカップ」の認知度アップの課題に取り組んだり、ドイツのケルンで、SDN(Service Design Network)のドイツセクターが主催のワークショップで、サービスデザインのワークショップに参加し高齢化社会の課題解決へのデザインを他の参加者と一緒にプロトタイピングをするなどして、研究材料を集めました。
また、勿来でのワークショップのオーガナイザーの方といわき地域で社会デザイン活動を行うグラフィックデザイナーの方にも改めて実践者としてのお話を聞くために、インタビューしました。これらの実践的リサーチからは、スケッチだけにとどまらずロールプレイや工作などを通じてビジュアライズすることがディフューズデザイン的なプロセスの中で対話を促すことを体験したり、対話やクリエイティブを引き出すためのツールなどが多く開発されたりしていることを学びました。一方、スキルと経験が場を支配してしまうことへの危惧であったり、ラフさの大切さを学ぶこともありえると気づきました。


このように集めた材料を、ダブルダイヤモンドというデザインプロセスを図解したフレームワークにフェーズごとに当てはめて、既存のセオリーや研究者の文献と照らし合わせながら再度観察しまとめました。
COOPでは研究の仕方も進め方も自分で決めることになります。指導教官と相談はしていましたが、正直、自分がやっていることが修士論文に値する研究になっているのか最後まで不安でした。クラスメイトと励ましあいながら書き上げ、口頭発表をして、無事卒業することができました。
(論文のアブストラクト:Selection of successfully completed Master´s Thesesをクリックすると見れます https://coopdesignresearch.de/#curriculum )
循環型経済を実装するベルリン発スタートアップでの新たなる挑戦
ドイツでは、外国人学生は、大学・大学院を卒業すると仕事を探すための猶予として、一年半のビザを申請できます(2019年9月時点)。優秀なクラスメートのなかには、論文執筆のかたわら就職活動をしていたメンバーもいましたが、私は当時、論文でいっぱいいっぱいで、就職活動をする余裕は持てませんでした。大学院の後半は論文に集中することにして、このビザを取得してから今後の身の振り方を考えようと決めました。
ソーシャルデザインの分野で実践知の強化と社会実装の経験を積みたいという思いが強くあり、これまでのキャリアである出版、広告、マーケティングの企業でアートディレクター・グラフィックデザイナーとして就職活動をするのは最後の手段にしました(経験があったとしても外国人としてその職を得ることは楽ではないとは思います)。
とはいえ、ツテもなく、自分で立ち上げたいプロジェクトがあるわけでもなかった私は、何を糸口に始めればいいか分からなかったです。ベルリンに戻ってからも、2ヶ月間は大学院の友人とカンファレンスに参加したり、ワークショップやミートアップに行ってみたり、とにかく人に会って、話してと模索していました。そんな折に、修士論文中に参加したあるワークショップのメンバーが主催するハッカソンに誘っていただき、そこで、DYCLE(ダイクル)というスタートアップのメンバーでもあるドイツ人女性に出会いました。これがきっかけとなり、今はフリーランスのデザイナーをしながらDYCLEのメンバーとしても活動しています。
DYCLEはプラスチックフリーの堆肥化できる赤ちゃんのオムツを開発し、サービス化することで、新たな循環型経済システムを実装しようとしているベルリン発のソーシャル・スタートアップです。DYCLE創業者の松坂愛友美さんのアートプロジェクトが発端となり、そのビジョンに共感したメンバーが集まり、テスト運営を重ねながらビジネス化に向けて活動しています。
赤ちゃんの排泄物は栄養価が高いのですが、DYCLEでは使用したオムツと一緒にこれを集め、炭と混ぜて、微生物の力を借りてコンポストすることで、質の高い市場価値のある土をつくり出します。それだけではなく、オムツの使用、コンポスト、土の利用、生産と、一つひとつの課程がつながり循環し、ビジョンを共有する人々が集まることで、コミュニティを生み育みます。

私は、DYCLEではサービスデザインとコミュニケーションツールなどのデザインを担当しています。間も無く1年ほど経つのですが、実際にソーシャルビジネネスを実装させることは、研究主体や学びが主目的のデザインプロジェクトと異なり、やってみたらとてもタフでした。
最初はサービスデザインのメソッドやセオリーにならってリサーチをしてみようと必死になっていました。実践経験の不足もあると思いますが、実務は教科書のようにはいかないですし、スタートアップにはリソース不足など現実的な問題も常について回ります。その分エキサイティングでもあるし、代表たちの姿勢や他のメンバーたちから学ぶこともたくさんありました。
グラフィックとサービスを並行して担当することもあるので、そのたびに自分の物事の見方が変わるのを体感しています。グラフィックの仕事をする場合、例えるなら森から木へとフォーカスを絞っていく感覚があるのですが、DYCLEでは木を見ることと、森を見ることを同時にしているような感覚です。また、価値を伝え、物を売るためのデザインの経験も無駄ではなかったと感じています。なので、最近は肩書きにこだわらずフレキシブルにいるように意識しています。
デザインリサーチの視点としては、ベルリンというローカルで始まったDYCLEのビジネスモデルが常態化して広がり、持続可能なオムツの選択肢を増やすことができたら、既存のシステムの連続性に変化を与えることになります。これは、先述の研究者マンズィーニが著作で紹介している「社会システムの変化を生むソーシャルイノベーション」に近い変化で、当事者としてソーシャルイノベーションを見ることができると期待しています。
また、DYCLEで活動するうちに、人間だけでなく地球中心とでも言えばいいのでしょうか──無理をせず、楽しく、地球のエコシステムとどう私たちの社会生活を共存していくか──が、これから取り組みたいテーマとして湧いてきています。母国である日本には元々自然と共存してきた文化があり、多くの人知が残っている土地でもあると思っているので、いずれ日本でも何かできたらなと、漠然とですが考えています。

ライター:佐藤ちひろ
グラフィックデザイナー・アートディレクター・駆け出しデザインリサーチャー。国内で広告・エディトリアル・マーケティング等の分野でグラフィック・ビジュアルコミュニケーションに従事したあと、2018年COOP Design Research (Msc)に入学。現在は、ベルリンのソーシャルスタートアップDYCLEでオムツの堆肥化をベースにした循環型経済プロジェクトに取り組む。
関連記事はこちら